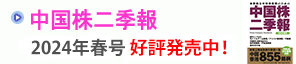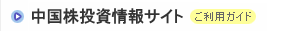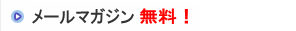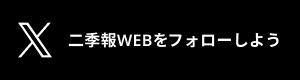| レポート > 一覧 |
| 2025-04-03 | 香港/トピック/証券 |
|
香港相場:1−3月の騰落率で世界トップ、米関税で4月以降の調整は避けられず
香港株式市場は3月下旬の下げで、31日には4週間ぶり安値を付けたが、それでも1−3月期のハンセン指数の値上がり率は15.25%(中国企業指数は16.8%高)。欧米、日韓などを上回り、世界の主要株価指標の中で頭一つ抜けた好パフォーマンスを達成した。米OpenAIの「GPT-01」に匹敵する中国発の高度AIモデル、「DeepSeek」の登場が、低迷続きの香港相場を大きく押し上げたきっかけ。中国ハイテクセクターの強さが意識され、先行きに対する楽観ムードが台頭。自前でAIを開発するアリババ集団(09988)を筆頭とするテック銘柄の再評価が一気に進み、ハンセンテック指数の1−3月の値上がり率は20.7%を記録した。
ただ、トランプ米政権が現地時間2日に発表した「相互関税」が衝撃となり、続く4月の相場に関しては慎重見通しが非常に強い。中国に対する相互関税率は大方の予想を超える32%とされ、4月の相場に対する慎重見通しが、一段と悲観的に傾いた。香港のウエルスマネジメント会社、ハーバーファミリー・オフィスの郭家耀業務発展総監は、相互関税の範囲と税率が予想を上回ったことで、市場は大きく反応すると予想。ハンセン指数が22500ポイントの支持線を試す展開を見込む。
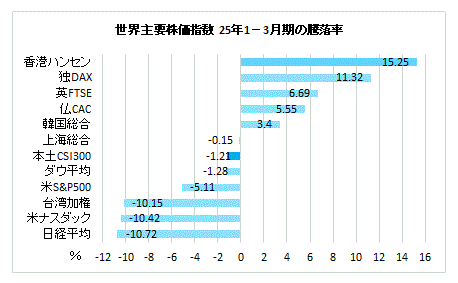
◆22500ポイントでの下値支持に期待、中国政府の対応策がカギに
『香港経済日報』の投資コラムも3日朝の速報で、ハンセン指数の22500ポイントでの下値支持を予想。仮にこのラインを下抜けた場合には21523ポイントが次の支持線になるとした(中国企業指数は7850ポイント)。中国政府が介入する、あるいはA株が急伸するなどの事態が起きない限り、当面は23000ポイントが上値抵抗線になるとみて、投資家に対し、底値拾いを急ぐことのないよう助言している。
ただ、同紙は、◇過激なトランプ関税は相手国経済だけでなく米国経済を害する、◇すでに米関税慣れした中国にとってはある程度想定済みであり、必ずしも重大な問題ではない――との可能性に言及している。本土・香港株式市場への影響の度合いはあくまで、「中国政府の対応策次第」との見方だ。
この局面での投資選択肢に関しては、中国国内ビジネスにほぼ特化している銘柄を挙げ、具体的には国有の通信株、電力株、有料道路株などが候補になるとの指摘。ほかにAIテーマ、クラウドテーマをはじめとするハイテク銘柄に関しても、トランプショックを受けた下落局面が買いチャンスにつながる可能性があるとしている。
◆1−3月の騰落率上位銘柄は明暗、アリババとBYDは「調整待ちの買い」推奨
1−3月期の香港市場を振り返ると、ハンセン指数銘柄の騰落率上位にはハイテク銘柄が並んだ。ランキングの首位は55.35高のアリババ集団。DeepSeekと自社開発LLM「Qwen(通義千問)」を活用したクラウド事業の成長期待が追い風となった。2位以下は、バイオ医薬品の開発受託会社である薬明生物技術(02269)、世界トップの新エネルギー車目メーカーBYD(01211)、中国最大のファウンドリーSMIC(00981)、スマホやIoT家電に加え、新規参入したEVで成功を収めた小米集団(01810)の順。それぞれ業績や業界サイクルに関する先行き見通し、政策の影響などが株価押し上げ要因となった。
『香港経済日報』はこの5社の4−6月期のパフォーマンスを予想しているが、全体相場を取り巻く不確実性が大きいこともあり、積極的な買い増し推奨はゼロ。うちアリババ集団とBYDの2銘柄に関してのみ、短期的な調整待ちの買いを推奨し、他3銘柄につては様子見を勧めている。
うちアリババ集団に関しては高度なAIモデルの融合によるクラウド業務の成長期待が続く見込み。また、新エネ車だけでなく、EVバッテリーを含む垂直メーカーのBYDは、全産業チェーンと技術的な優位が際立ち、最近では高度運転支援システム「天神之眼(God's Eye)」を全シリーズに搭載すると発表。さらに「5分で充電可能」という画期的なEVバッテリーを発表し、市場では一段の販売増に対する期待が高まっている。
半面、薬明生物技術は、22年に35%安、23年に50%安、24年に40%安と、極めて低調に推移した後、25年1−3月期には54%高。決算の予想上振れを受けて持ち直したが、同社の場合は北米企業が主要取引先であるということが最大の弱点であり(売上高の57%が米国向け、23%が欧州向け)、明らかに米関税リスクに直面している。また、SMICは最近、大株主のキン芯(香港)投資が持ち株売却に動いたことで投資心理が後退。小米集団は3月下旬に発表した増資に加え、EV「SU7」の自動運転走行中の死亡事故がマイナス材料となっている。
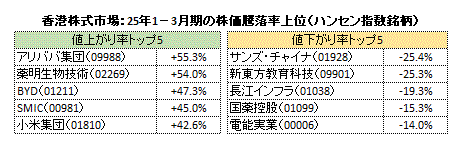

ただ、トランプ米政権が現地時間2日に発表した「相互関税」が衝撃となり、続く4月の相場に関しては慎重見通しが非常に強い。中国に対する相互関税率は大方の予想を超える32%とされ、4月の相場に対する慎重見通しが、一段と悲観的に傾いた。香港のウエルスマネジメント会社、ハーバーファミリー・オフィスの郭家耀業務発展総監は、相互関税の範囲と税率が予想を上回ったことで、市場は大きく反応すると予想。ハンセン指数が22500ポイントの支持線を試す展開を見込む。
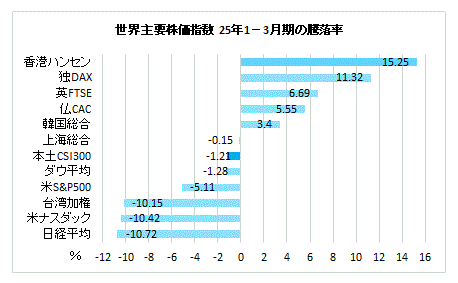
◆22500ポイントでの下値支持に期待、中国政府の対応策がカギに
『香港経済日報』の投資コラムも3日朝の速報で、ハンセン指数の22500ポイントでの下値支持を予想。仮にこのラインを下抜けた場合には21523ポイントが次の支持線になるとした(中国企業指数は7850ポイント)。中国政府が介入する、あるいはA株が急伸するなどの事態が起きない限り、当面は23000ポイントが上値抵抗線になるとみて、投資家に対し、底値拾いを急ぐことのないよう助言している。
ただ、同紙は、◇過激なトランプ関税は相手国経済だけでなく米国経済を害する、◇すでに米関税慣れした中国にとってはある程度想定済みであり、必ずしも重大な問題ではない――との可能性に言及している。本土・香港株式市場への影響の度合いはあくまで、「中国政府の対応策次第」との見方だ。
この局面での投資選択肢に関しては、中国国内ビジネスにほぼ特化している銘柄を挙げ、具体的には国有の通信株、電力株、有料道路株などが候補になるとの指摘。ほかにAIテーマ、クラウドテーマをはじめとするハイテク銘柄に関しても、トランプショックを受けた下落局面が買いチャンスにつながる可能性があるとしている。
◆1−3月の騰落率上位銘柄は明暗、アリババとBYDは「調整待ちの買い」推奨
1−3月期の香港市場を振り返ると、ハンセン指数銘柄の騰落率上位にはハイテク銘柄が並んだ。ランキングの首位は55.35高のアリババ集団。DeepSeekと自社開発LLM「Qwen(通義千問)」を活用したクラウド事業の成長期待が追い風となった。2位以下は、バイオ医薬品の開発受託会社である薬明生物技術(02269)、世界トップの新エネルギー車目メーカーBYD(01211)、中国最大のファウンドリーSMIC(00981)、スマホやIoT家電に加え、新規参入したEVで成功を収めた小米集団(01810)の順。それぞれ業績や業界サイクルに関する先行き見通し、政策の影響などが株価押し上げ要因となった。
『香港経済日報』はこの5社の4−6月期のパフォーマンスを予想しているが、全体相場を取り巻く不確実性が大きいこともあり、積極的な買い増し推奨はゼロ。うちアリババ集団とBYDの2銘柄に関してのみ、短期的な調整待ちの買いを推奨し、他3銘柄につては様子見を勧めている。
うちアリババ集団に関しては高度なAIモデルの融合によるクラウド業務の成長期待が続く見込み。また、新エネ車だけでなく、EVバッテリーを含む垂直メーカーのBYDは、全産業チェーンと技術的な優位が際立ち、最近では高度運転支援システム「天神之眼(God's Eye)」を全シリーズに搭載すると発表。さらに「5分で充電可能」という画期的なEVバッテリーを発表し、市場では一段の販売増に対する期待が高まっている。
半面、薬明生物技術は、22年に35%安、23年に50%安、24年に40%安と、極めて低調に推移した後、25年1−3月期には54%高。決算の予想上振れを受けて持ち直したが、同社の場合は北米企業が主要取引先であるということが最大の弱点であり(売上高の57%が米国向け、23%が欧州向け)、明らかに米関税リスクに直面している。また、SMICは最近、大株主のキン芯(香港)投資が持ち株売却に動いたことで投資心理が後退。小米集団は3月下旬に発表した増資に加え、EV「SU7」の自動運転走行中の死亡事故がマイナス材料となっている。
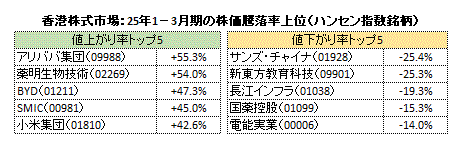

| ※過去6カ月の記事タイトルがご覧いただけます。 |
| 121〜180件を表示します(合計272件) |
| 1 2 3 4 5 |
|
| 121〜180件を表示します(合計272件) |
| 1 2 3 4 5 |
|